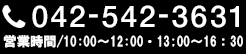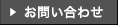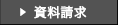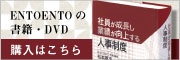第252話 利他主義賃金制度へのバージョンアップ
2025-04-02
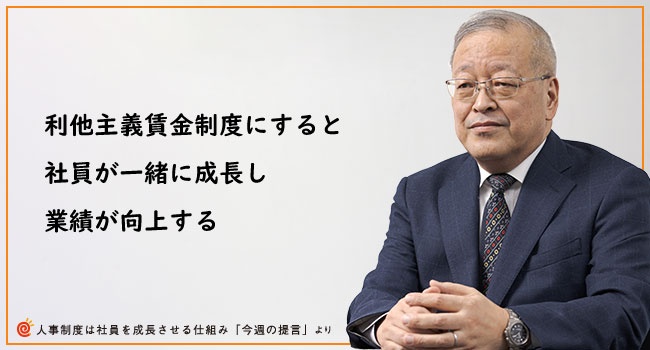
一般的な賃金制度では、社員を「利己主義」にしてしまう恐れがあります。
賃金制度を導入する企業の経営者が、社員に対して「頑張った社員には昇給・賞与をたくさん出します」と説明していれば、社員は徐々に利己主義になっていきます。しかも、その利己主義になる社員は「組織原則2・6・2」における上位2割の優秀な社員であるために組織上の問題は大きいのです。
「成果の高い社員に昇給・賞与をたくさん出す」という発言が、どうして社員を利己主義にするかご不明な方もいるでしょう。それは、社員数が何名いたとしても、昇給・賞与を最も多くもらえる社員はたった一人だからです。それ以外の社員はトップの社員と比べると昇給・賞与が少ないことになります。
成果の高い社員の昇給・賞与が多いと言うのであれば、社員はその昇給・賞与の金額が自分の評価を表していると考えるのは当然のことです。社員は、自分の昇給・賞与が社内でどれぐらいの順番なのかとても気になるでしょう。他の社員と比較したいと思うかもしれません。特に、一生懸命仕事に取り組んでいる社員ほど「自分は経営者から高く評価されていて、昇給・賞与も高いはずだ」と思います。
ところが、トップの社員はたった一人で、それ以外はトップと比べると昇給・賞与は少なくなるのが現実です。トップの社員以外はその現実を知り、徐々にモチベーションを下げてしまうでしょう。
もし、今まで以上の成果を上げるやり方を見つけたとしても、全社員に共有化することはありません。自分がそのトップになるためには教えることは不利だと思ってしまうからです。現時点でトップの社員も、成果を上げるやり方を誰にも教えないようになっていくでしょう。
結局、全ての社員が昇給・賞与をたくさんもらおうとして、成果を上げるやり方を他の社員に教えようとはしなくなるのです。そうなってしまうと、会社は継続して業績を上げることは困難です。
このような賃金制度を導入したことで、社員は成果を上げるやり方を共有化することが無くなり、社員間の成果の差は大きくなっていきます。その結果、会社全体の業績は悪くなり、昇給・賞与は全体的に減少する傾向になります。これが、一般的な賃金制度の弊害です。
これからは社員が「利他主義」になるような賃金制度が必要です。
「成果が高い社員には昇給・賞与をたくさん出す」という説明から「会社の業績が高くなれば【全社員】の昇給・賞与がたくさん出せる」と説明できる仕組みに変えなければなりません。
個人の成果の高さはもちろん大切ですが、会社の業績が良くなければ昇給・賞与をたくさん出すことはできません。このことを説明できる賃金制度が必要になりました。
特に今、昇給に関しては「賃上げ率」という言葉が日本中に広まっています。逆にこの「賃上げ率」を活用することで、全ての社員を利他主義の社員にすることができます。なぜなら、組織原則2・6・2があったとしても、全ての社員が共通に「賃上げ率」の恩恵を受けることができるからです。
最近の大手企業が掲げている賃上げ率5%を実現するためには、これまで以上に業績を伸ばしていかなければなりません。業績が厳しい状況で昇給し続けることはできないからです。
そこで、昇給に関しては経営目標の発表時に「この経営目標を実現できたら○%賃上げする。さらにそれ以上の経営目標を実現したときには5%賃上げする」といったように、高い賃上げ率を実現するにはどれだけ業績を上げなければならないのかを併せて発表します。
中小企業の今までの賃上げ率が仮に平均2%弱だとすれば、実に今までの2.5倍の賃上げ率ですから、経営目標が高くなることは間違いありません。5%の賃上げ率を実現するためには、これまで以上に高い経営目標の達成が求められるでしょう。
しかし、全社員が一緒になって賃上げ率5%を実現したいと考えたときの行動は、ほとんど同じです。お互いに教え合い、助け合って高い経営目標を実現しようとします。
成果を上げるやり方があれば、それを他の社員に教えるようになるでしょう。社員は個人で成果を上げるよりも、会社全体で成果を上げることが高い賃上げ率につながると理解するからです。
ただし、このとき「他の社員に教えた社員を最も高く評価する」ことを社員には明らかにしておく必要があります。成果の高い社員は他の社員に教えることで高く評価され、成果の低い社員は成果を上げられるやり方をどんどん教えてもらうことで、全社員が成長していくことになり、より成果を上げるやり方に注力するようになるでしょう。
つまり、このときの経営者の発言は「全ての社員が一緒にこの会社で成長して業績を上げ、全員で高い賃上げ率5%を獲得しよう」となるのです。どうぞこの賃上げ率を上手に使って全社員を成長させてください。
全ての社員を利他主義にするためのENTOENTO式人事制度は、グループコンサルティング成長塾で作成できます。賞与についても同様に、会社全体が一丸となって高い賞与の実現を目指すようになります。
資料の請求は簡単です。ご関心のある方はどうぞ成長塾の資料をご請求ください。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
※ 成長塾についてはこちら ※ 資料請求はこちら ※ 松本順市の書籍はこちら